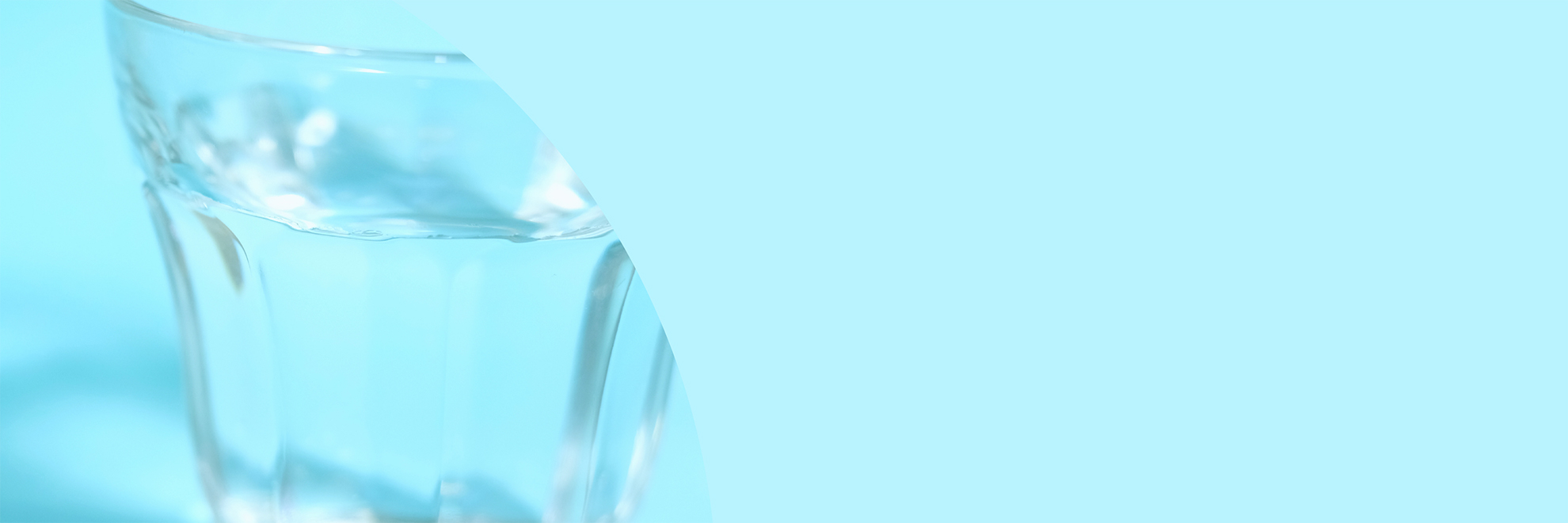
雨水が飲水になるまでの過程や、成分などをご紹介します。
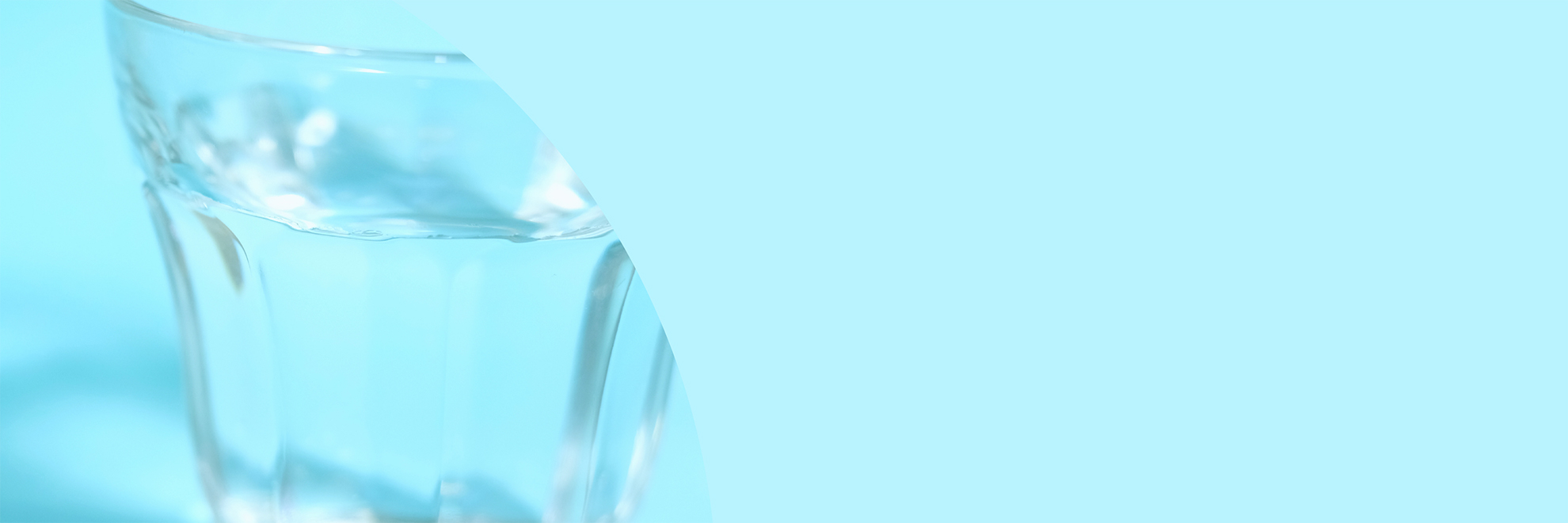
雨の成分と飲水になるまで
雨は私たちの生活において欠かせない水源の一つです。
雨水がどのように形成され、飲み水という形となって我々の元に届くのかを紹介します。
その前にまず、雨が何でできているのかを知りましょう。
雨の成分とは

雨の主成分は水です。
そして、大気中の窒素、二酸化炭素などを含んでいます。
降っている場所によっては、雨には塩素、ナトリウム、アンモニウム、カルシウムなどの成分も含まれることがあります。
また、降っている最中に、空気中の不純物を取り込みながら地上に降り注ぎます。
雨が降って飲み水になるまで
まず、太陽の熱により、海、湖、川などの水が蒸発し、水蒸気として大気中に上昇します。
上昇した水蒸気は、気温が下がる高度や冷たい空気と出会うことで凝結し、小さな水滴となります。
この集合体が雲となり、大気中に浮かんでいるのです。
雲の中では水滴が増え、重くなると地上に降り注ぎます。
これが雨です。
地上に降った雨は、さまざまな経路によって地下に浸透します。
地下に染みて地下水となるものもありますが、それ以外は地表を流れて川や湖に注がれ、貯水湖に貯められていくのです。
飲用水として利用されるためには、雨水や地下水の浄化処理が必要です。
浄水場や水処理施設では、濾過や消毒などの工程を経て、細菌や有害物質を取り除きます。こうして処理された水は、安全な水道水として供給されます。
人が飲める水は地球上にどれくらいある?
地球上には14億km³の水が存在しているとされますが、そもそも人間が飲めるような水は一体どれくらいあるのでしょうか?
総水量14億km³のうち、97.5%は海水です。
淡水は残りの2.5%で、そのうちの約70%は北極や南極に浮かぶ氷雪だとされています。
更に、残り30%の大半が地下の奥深くに染み込んだ地下水です。
人間が現実的に飲み水として利用できるものは、全体のたった0.02%といわれています。
参考:https://www.apiste.co.jp/contents/water/chapter01.html
たった0.02%ですが、その僅かな水は循環を繰り返して絶え間なく供給されており、水を使いすぎて人々の飲み水がなくなることはまず有り得ません。
しかし、有限の資源であるという事実は変わらないでしょう。
コラム:水はどこからやってきた?
水の惑星の異名を持つ地球ですが、最初から水に満ちた星ではなかったといわれています。
では、水は一体どこからやってきたのでしょうか?
まだ断定できるような有力説はなく、水の起源については今でも議論されています。
世界中の研究チームが研究し続けているなかで、いくつかの有力な説を紹介していきましょう。
- 小惑星や彗星の衝突
- 火山活動
- 太陽系星雲ガス
地球が形成された初期に、はるか遠くからやってきた小惑星や彗星が地球に衝突し、水をもたらしたという説です。
現在最も有力な説の一つであり、地球上を覆う海はこのときに激突した惑星由来のものとされています。
地球が形成された当初は火山活動が盛んであり、その過程で水蒸気が発生し、雨となって地球に降り注いだという説です。
この水が地表に蓄積され、海や湖などの水域が形成されたと考えられています。
地球が形成された後、太陽系星雲ガスによって水がもたらされたという説です。
星雲ガス中には水分子が存在し、地球の形成にも影響を及ぼした可能性があります。
これらは一つの要素だけでは説明がつかず、複合的な要因によるものという見方が主流です。
どの説にせよ、はるか昔から地球と水は切っても切り離せない関係なのは変わりません。
限りある資源を大切に
海や川が水蒸気となり、雨として降り注ぐという循環は、私たち人間が生まれるよりもずっと昔から続いてきました。
有史以前から数えきれないくらいの生き物たちが水を消費してきましたが、まだ尽きる様子はありません。
これからも、人間は水とともに生きていくことでしょう。
しかし、渇水に苦しむ地域が存在することも忘れてはいけません。
循環を繰り返しているとはいえ、水は限りある資源であり、節約しながら大切に使っていく必要があります。
持続可能な水の利用を心がけましょう。
